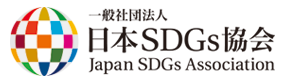2025.09.14
講演記録②:吉條嘉家氏「SDGsの理念と中小企業にできること」
2025年7月30日に開催された2025年度第1回公開セミナーのなかから、吉條嘉家氏(日本SDGs 協会専務理事)の講演内容を全文記録したものです。

2025年7月30日に開催された2025年度第1回公開セミナー(共同開催:一般社団法人日本SDGs 協会/いのち会議/大阪大学SSI車座の会)のなかから、吉條嘉家氏(日本SDGs 協会専務理事)の講演内容を全文記録したものです。
セミナーの開催記録については、以下の活動報告をご覧ください。
2025年7月30日:2025年度第1回公開セミナー 開催記録
なお、同セミナーでは、以下の2つの講演も行われました。ご参照ください。
講演記録①:堂目卓生氏「共助社会と共感経済――『いのち会議』の理念と活動」
講演記録③:伊藤武志氏「新たな共感経済・共助社会をどうつくるか」
SDGsの理念と中小企業にできること
日本SDGs協会専務理事
吉條 嘉家 氏
0:最初に
本日は多くの皆さまにお集まりいただき、まことにありがとうございます。
連日、「災害級の暑さ」と言われています。本日もそうですけれども、気候変動がこれまでの私たちの予想を超えて、非常に速いペースで進んでいることを、肌身をもって感じる毎日です。人間の活動が地球環境に過度の負荷をかけ、このままでは人が住み続けることが難しい状況になりつつあるのではないか、と実感してしまえるようになりました。一方で世界を見渡すと、先進諸国と途上国、紛争地域に暮らす人々との間には、想像を絶する格差や不平等が存在しています。
こうした大きな問題に対して、SDGsは、全世界の国々が一致協力して「将来世代も含め、誰一人取り残さない」社会をつくる、そのための17の具体的目標として、2015年に採択されました。今の社会を変えていこう、という理念の下にある枠組みです。
しかしながら、そういった世界的な環境問題や人権問題について、中小企業に何ができるのかと考えると、なかなかできることが見つからないように思いますよね。とはいえ、戦後のベンチャーの歴史を振り返ると、ソニーも京セラもホンダも、もともとは小さな町工場からスタートしました。小さな経営基盤しかない私たち中小企業にも、できることがあるはずです。今日はそれを考えてみたいと思います。
1:自己紹介
ここで、少し自己紹介をさせてください。私は、父が創業した玩具メーカーで、1995年から2018年頃まで役員を務めました。入社翌年の1996年、京セラ創業者の稲盛和夫さんが主宰する「盛和塾」で、京セラフィロソフィーという理念を学びました。年商7,000万円ほどで大幅な欠損が出ていた零細企業を、23年で年商12億円まで成長させ、2002年には「稲盛経営者賞」をいただきました。経営は、最終的には“経営者の思い・理念”が要である――それを、現場で骨身にしみて学ぶことができました。
日本SDGs協会_ページ_02-1024x576.jpg)
日本SDGs協会_ページ_03-1024x576.jpg)
「稲盛経営者賞」をいただいた2002年頃、当時コロンビア大学教授だったジェフリー・サックス先生の『貧困の終焉』を拝読しました。また、ちょうど2000年から、国連ではMDGs(ミレニアム開発目標)が始まっていました。SDGsの前身にあたる取り組みです。
ジェフリー・サックス先生という一人の思想やアイデアが国連を動かし、世界を動かし、貧困の撲滅に挑んでいく――その姿に大きな感銘を受け、そこから国連の活動に注目するようになりました。これが、のちに私と日本SDGs協会とのご縁にもつながっています。
日本SDGs協会_ページ_05-1024x576.jpg)
2:SDGsの歴史的経緯
MDGsは、主にアフリカをはじめとする貧困国が、発展のための最初のステップに足をかけられるよう、先進国が支援する「開発目標」でした。ただ、仮に諸国が経済発展を遂げ、日本やアメリカ並みの生活水準に近づくことができたとして、地球環境は持ちこたえられるのか。ここに環境問題という、根源的な問いがあります。例えば化石燃料の枯渇、化学物質の問題です。
環境問題の先駆け的な書籍であるレイチェル・カーソンの『沈黙の春』(1960年代)が化学物質による環境汚染を早くから警鐘を鳴らしています。当時は南極の一部に化学物質が検出されない“最後の聖域”もありましたが、いまやマイクロプラスチックや農薬が完全に世界中に蔓延しています。またバックミンスター・フラーの「宇宙船地球号」という言葉の通り、私たちは一つの地球という船に乗っている。燃料が枯渇すれば立ち行かない。私たちが子どもの頃、「石油は掘りすぎるとなくなるよ」と言われましたよね。そして最近特にクローズアップされているのが地球温暖化問題です。1992年の地球サミット以降は、温室効果ガスの増加、オゾン層の破壊といったテーマが世界的な議題になってきました。
つまり、サステナビリティの観点を無視して貧困対策だけを進めれば、経済発展と環境保全がトレードオフになってしまう。そこに配慮しながら開発を進めるために、2015年にSDGsが生まれました。MDGsの8つの目標が広い文脈で引き継がれ、社会・経済・環境の領域がさらに拡張されて、17の目標から成るSDGsになった――おおまかな歴史の流れは、こういうことだと思います。
日本SDGs協会_ページ_07-1024x576.jpg)
日本SDGs協会_ページ_08-1024x576.jpg)
3:SDGsと資本市場・産業界の動き
SDGsの広がりと並行して、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資という投資基準が形成され、世界の機関投資家が重視する指標になりました。日本でもGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2015年にPRI(国連責任投資原則)に署名し、ESG投資が広がっています。結果として、大企業がサプライチェーン全体でESG基準の最適化を進めるなかで、中小企業にも行動基準の整備が求められる局面が増えています。
同時に、若年層の就職市場でも、企業のSDGs・ESGへの姿勢は重要視されるようになりました。つまり中小企業は、上流の大企業からも、将来の人材からも、「SDGsにどう取り組むか」を問われる時代に入っている、ということです。
先程の堂目先生のお話でもご指摘のあった通りですね。
日本SDGs協会_ページ_29-1024x576.jpg)
4:京セラフィロソフィーとSDGs
しかしながら、そのSDGsの大きな理念を、私たちはどう実現していくのか。正直、私たちに今できることは限られています。例えば、ガザの人道危機を、いきなり私たちだけで解決することはできませんし、温暖化を食い止める新たな手段をすぐに開発できるわけでもない。そう考えると、SDGsが重荷に感じられ、最低限の対応を行っておくことでお茶を濁しておこうと考えがちではないでしょうか。
しかし、私たちが心しておかなければならないことは、まず身の回りから始めることです。そこで私は、「盛和塾」での学びを思い起こします。
稲盛先生が掲げる京セラフィロソフィー(企業理念)は、「経営理念:全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、 人類・社会の進歩発展に貢献すること」です。実はこの理念、当初は「従業員の物心両面の幸せを追求する」だけだったようです。しかし、それだけでは卑近で広がりがないので、あとから後段を付け加えられたんですね。稲盛さんご本人が語っておられたのを、とても印象的に覚えています。
しかし、この理念が、その後の成功を導きます。もうこの理念“一本槍”で、稲盛さんは京セラという会社をつくり、世界企業に育て、KDDIを創業し、JALの再生にも携わった。
京セラには「経営の原点12カ条」など数々の指針がありますが、根っこには「深層心理に透徹するような強い思いを持つ」ことがあります。人が本気で思いを馳せて行動できる対象は、実は限られている。だからこそ、身近な対象に向けた強い思いが、いちばん実践につながります。いま隣で頑張ってくれている従業員や仲間のために頑張ろう、という思い――これは強いですよね。それが「人類・社会の進歩発展に貢献」に繋がるわけです。SDGsのために私たちができることも、これと同じ道筋ではないでしょうか。
日本SDGs協会_ページ_34-1024x576.jpg)
5:企業の価値とSDGs
SDGs採択の基本理念は、「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」、そして「持続可能でよりよい社会の実現」です。私たち流に言い換えれば、お客様・取引先・従業員・将来世代の子どもたち――すべての利害関係者が持続的に幸せに暮らせる価値を実現することでしょう。日本にはもともと、「世のため人のため」・「情けは人のためならず」、「利他の精神」・「三方よし(売り手よし・買い手よし・世間よし)」という、SDGsと親和性の高い価値観が根づいています。ここを自社の言葉で呼び起こすことが、最初の一歩になります。
日本SDGs協会_ページ_33-1024x576.jpg)
要は、身近な人を幸せにすることです。顔の見える家族や従業員の幸せをどう実現するか。そのために売上と付加価値を高め、昇給や生活の安定を保証できる土台をつくる。これを自分の保身ではなく、従業員のためにやり抜くとき、経営者は愛があり、同時に厳しい意思決定ができると、私は信じています。
もし自社に企業理念・社是があるなら、ぜひSDGsの17目標と突き合わせてみてください。必ずどこかに響き合う領域が見つかります。そこから、自社の事業領域と“身近な目標”を設定し、ステップ・バイ・ステップで、壮大な目標に近づく道筋を描いていく。それはすなわち、身近な人を幸せにしながら、盤石で持続的な成長の土台を築く営みそのものです。
従業員が安心して、やりがいを持って、定年まで働ける。従業員が、自分の子どもをまた自分の会社で働かせたいと思える。そういう会社は、すでに社会的に高い価値を持っています。取引先にはより高い付加価値が生まれ、地域社会に貢献できる事業基盤も育ちます。さらに事業規模が大きくなれば、いまの私たちには手に負えないと感じられるような、世界的な課題にも挑戦できる。こういう順番で力がついていくのでしょう。
日本SDGs協会_ページ_35-1024x576.jpg)
6:私の失敗と学び
とはいえ、人は小さな成功で満足してしまう。私自身、かつて年率20%くらいで事業が伸び、賞もいただき、自己中心的で傲慢になってしまった部分もあったように思います。結果、創業社長である父との関係もうまくいかななってしまい、天職だと思っていた玩具メーカーの仕事を離れざるをえなくなってしまいました。ただ、そこでの経験は現在の活動にも確実に生きています。
例えば、零細企業でしかなかった私の会社が大企業と戦うために必要だったのがITでした。当時は、Windows 95が出て、パソコンが普及し、ITの力が一気に伸びました。このDXを大いに活用したのです。これは、ディーセント・ワーク(SDG8)の創出にもつながり、格差是正(SDG10)にも寄与します。いま私は公認会計士として、本業でDXの支援に取り組んでいますが、身近な人を幸せにするという「盛和塾」での学びと経験が、SDGsへ向けた活動に間違いなく活きているわけです。
7:日本SDGs協会の役割――想いを、つなぐ
SDGsの完全な達成は、現時点の科学技術や企業の力だけでは難しい部分があることは明白です。だからといって、そこで諦めてしまったら、人類の存続のほうが危うくなるジレンマを抱えている。だからこそ、先ほど堂目先生のお話にあった「共感の経済」は、私たちに大きな示唆を与えてくれます。現在の私たちが考えうる論理だけでは越えられない壁があっても、「想い」は無限に広がり、それは「共感」に繋がります。その想いをどう“つなぐ”か。ここに、私たちの日本SDGs協会の役割があります。
SDGsは、上下関係ではありません。多様性を尊重し、互いを認め合い、それぞれの個性・特技を生かす。堂目先生の話にもあったように、立場はいつでも入れ替わり得る。自分ができることをやり、貢献したことが、また喜びとなって返ってくる。そういう「共感」と「共生」の経済が、私たちの大きなヒントになる――私はそう感じています。
日本SDGs協会は、「SDGsのすべてをわかっています」「こうすればよいのだという指針を示します」という組織ではありません。自らの取り組みをSDGsに照らして言語化し意義づけ、互いがフラットな関係で語り合いながら認め合い、そして強みを生かして協力することができる、いまの中小企業がさらに大きな課題に取り組むためのプラットフォームでありたい。今後も、皆さんのご協力をいただきながら、社会を変えていく――そんな夢を語り合い、想いをつなぎ、そして実現していく場でありたいと思います。
本日は、どうもありがとうございました。