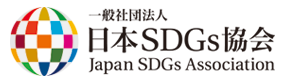2025.09.14
講演記録③:伊藤武志氏「新たな共感経済・共助社会をどうつくるか」
2025年7月30日に開催された2025年度第1回公開セミナーのなかから、伊藤武志氏(大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI))の講演内容を全文記録したものです。

2025年7月30日に開催された2025年度第1回公開セミナー(共同開催:一般社団法人日本SDGs 協会/いのち会議/大阪大学SSI車座の会)のなかから、伊藤武志氏(大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI))の講演内容を全文記録したものです。
セミナーの開催記録については、以下の活動報告をご覧ください。
2025年7月30日:2025年度第1回公開セミナー 開催記録
なお、同セミナーでは、以下の2つの講演も行われました。ご参照ください。
講演記録①:堂目卓生氏「共助社会と共感経済――『いのち会議』の理念と活動」
講演記録②:吉條嘉家氏「SDGsの理念と中小企業にできること」
新たな共感経済・共助社会をどうつくるか
大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI)
伊藤 武志 氏
0:はじめに
皆さま、本日はご参加ありがとうございます。先ほどの吉條さんの講演に続いてお話しします。
まず、お配りした資料についてご説明します。これは、SDGsの169のターゲットをまとめた一覧です。私は昨年から「SDGs+ビヨンドのための共感経済づくり」という授業を担当しており、学生にも同じ資料を共有しています。
「SDGs」という言葉は、すでに95%以上の方がご存じだと思いますが、ターゲット本文を実際に読んだ方は多くないのではないでしょうか。最初の一つ二つを読んでみると長くて覚えきれず、途中で読むのをやめてしまうという声をよく聞きます。そこで、各小項目をニ十数文字程度に圧縮して一覧しやすくしました。
授業では、この資料を使いながら、「興味があるところはどこですか?」と学生に尋ねます。また、講演などでは、製造業の方だったり、サービス業の方だったり、金融機関だったり、さまざまな違った分野の方がいらっしゃいますので、「事業に関係するところはどこですか?」と尋ねながらチェックしてもらったりしています。読みやすくしてありますので、まずは全体を一度通してご覧ください。今はAIがあり検索も容易ですが、全体に目を通してからそれぞれのゴールに戻ると、各項目の違いや関係に気がつきますし、全体の趣旨が立体的に理解できるようになります。いかがでしょうか。
ぜひ、日々の業務に活用していただければうれしく思います。
先ほど吉條先生が、稲盛先生についてお話してくださいました。私も、稲盛先生を尊敬しております。実は、今日の会場であるこのフロアも、稲盛財団からのご寄付で整備されています。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、将来の子どもたちのためにということで、SDGsを意識したいろいろなものが置かれています。まさに今日の趣旨にぴったりの場なんですね。学習用のゲームもございます。よろしければお手にとってみてください。いまは素晴らしいゲームがたくさん生まれておりまして、子どもたちはもちろんですが、大人の方でも、こうしたゲームで体験を通じて考えると、やはり理解が深まります。「やっとわかった」と、腑に落ちる瞬間が生まれるんですね。授業でも取り入れておりまして、SDGsだけでなく、社会全体を学ぶ機会になっています。
1:企業の公器性
さて、SDGsと企業に関して、少し振り返ってみます。
実は、1960年代末から企業の公器性、つまり企業の社会貢献が議論され始めました。そういった影響もあったと推測されますが、オムロン創業者の立石一真さんが、1974年の著書で、すでにこのように明確に述べられています(スライド参照)。
日本SDGs協会_ページ_02-1024x724.jpg)
要するに、ステークホルダーに向き合う経営を実践しようということですね。今日の吉條先生のお話に大いに通じることでもあります。いまここにいる私たちにとっては馴染みのあることかもしれませんが、社会全体にとっては必ずしも当たり前ではありません。学生もそうですし、先生方もしばしばそうですが、社会には、「企業は自分のためだけに営利を追求する」という思い込みが強くあります。例えば、堂目先生が「経済学は民を救うための学問です」とお話になると、学生が「えっ!」と驚く場面もあるんですね。それを本来の姿に近づけるには、こうした考え方を繰り返し伝えることが大切だと考えています。
2:分業とステークホルダーへの貢献
私の考えはシンプルです。会社という生業は、社会のために良いものやサービスをつくり、同時に正当に儲けます。その儲けは自分のためだけでなく、皆のためにも使われます。これが「生業」の意味であり、「会社」の意味です。こうした考え方を子どものころから学び、感じてもらいたいと思っています。
日本SDGs協会_ページ_03-1024x724.jpg)
私たちは役割分担を通じて社会を支えています。お金の面でも、生産の面でも同じです。堂目先生のご指摘の通り、支出面ではおよそ70%かもしれませんが、生産面では民間が約80%ですね。およそ家計が約15%、企業が約60%です。それから、NPOが約1%、政府セクターが約20%です。
堂目先生がご専門のアダム・スミスの『国富論』が説くように、それぞれの仕事が役割を分担し、良いものを作り、GDPを生み、さらにそれを分配していきます。資本主義が良い悪いという単純な話ではありません。数千年前に生まれた貨幣経済の誕生とともに商品経済が生まれ、私たちはその仕組みを使ってきましたし、これからも有効に使う必要があります。
日本SDGs協会_ページ_04-1024x724.jpg)
3:外部性とSDGs
しかし一方で、生物多様性、炭素、化学物質など、まじめに商売をしていてもどうしても生じてしまう問題があります。外部性と呼ばれるものですね。人口の増加も重なり膨らんでいくこういう問題を、なんとか皆で解決しなければならないという課題が、SDGsにつながります。
日本SDGs協会_ページ_06-1024x724.jpg)
学生には、会社やNPOの仕組み、働く人がどこに位置づくのかを伝えるための図も示しています。会社、国、NPOに対する共感に基づいて、私たちがどう行動すべきかを考えるシートです。
日本SDGs協会_ページ_07-1024x724.jpg)
4:良い企業を選び、良い企業を作ること
良い会社を作ることは、生産者である私たちの役割です。そして、選ぶ側もやっぱり私たちで、消費者も良い会社を選ぶことが必要です。きちんと良い会社を見極めて、良い会社を選んでいくことができれば、世の中はどんどん良くなっていきます。とはいえ、これまではそれがなかなか難しかったのも事実です。良い会社を選ぶための情報が、なかなか手に入らなかったからです。
しかし、現代では企業情報が透明化され、生産者と消費者の間の非対称性が徐々に解消されつつあります。認証・認定制度なども、そのひとつです。私たちでも、企業のESGレベルを測る活動を進めています。正直な開示があれば、企業の活動を見極められる時代です。そのためのアプリケーションの開発も進めています。こうした活動を広げ、皆で切磋琢磨してレベルを上げていきたいと考えています。
日本SDGs協会_ページ_09-1024x724.jpg)
5:まとめ
最後に、堂目先生の示されたチャートをまとめておきたいと思います。
私たちみんなが共感をもち、企業の内側で働く人もいれば、外側から支える人もいます。みなの活動が、みなを支えるという仕組みであり、その働きが社会を支えます。共感をベースにESGを追求する必要があります。実のところ、経済というものがそのように進んできたわけですが、SDGsは、そのレベルをさらに上げていく取り組みです。
日本SDGs協会_ページ_10-1024x724.jpg)
以上です。ご清聴ありがとうございました。