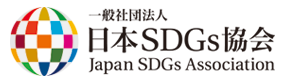2025.09.14
講演記録①:堂目卓生氏「共助社会と共感経済――『いのち会議』の理念と活動」
2025年7月30日に開催された2025年度第1回公開セミナーのなかから、堂目卓生氏(大阪大学総長補佐)の講演内容を全文記録したものです。
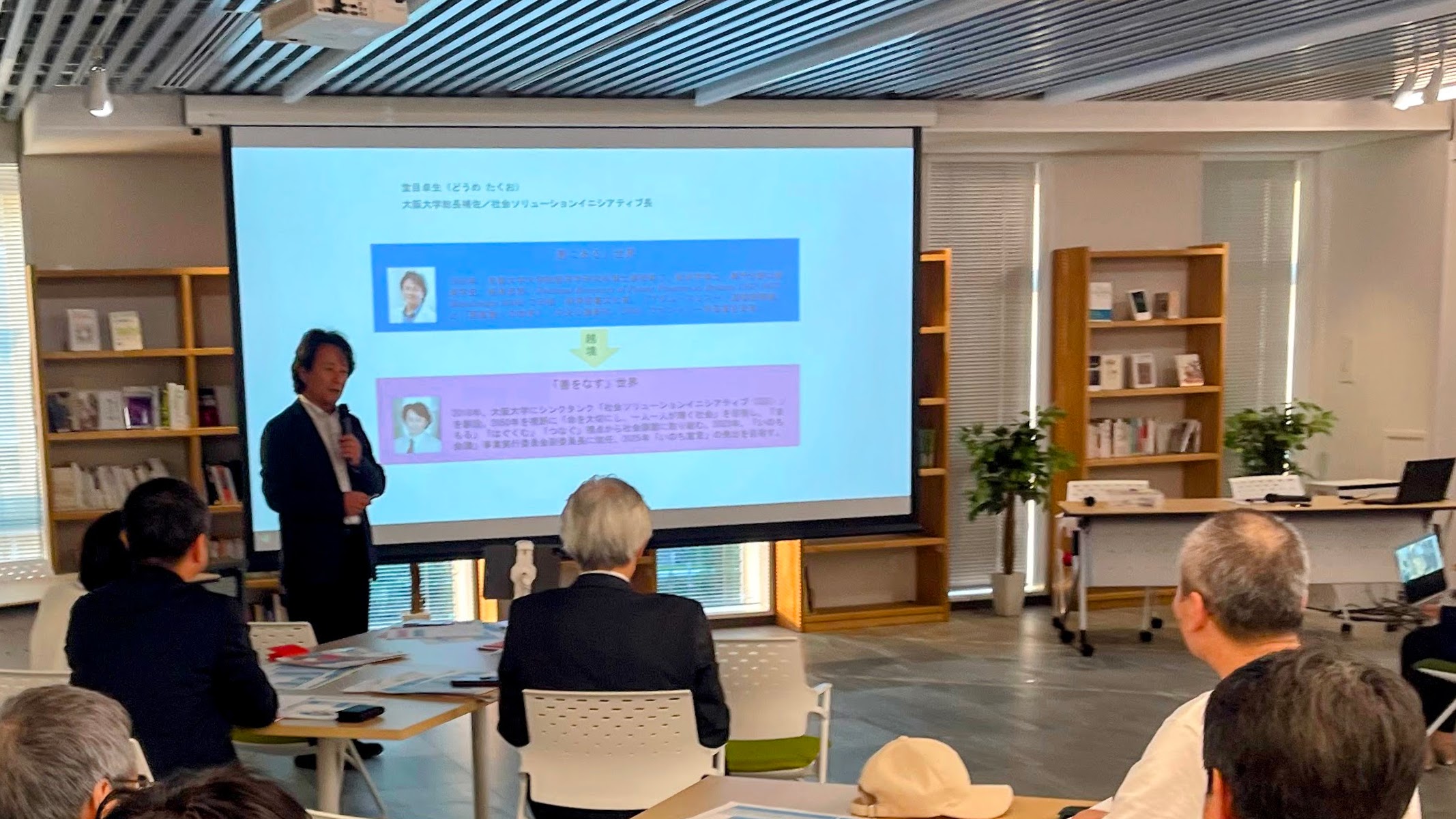
2025年7月30日に開催された2025年度第1回公開セミナー(共同開催:一般社団法人日本SDGs 協会/いのち会議/大阪大学SSI車座の会)のなかから、堂目卓生氏の講演内容を全文記録したものです。
セミナーの開催記録については、以下の活動報告をご覧ください。
2025年7月30日:2025年度第1回公開セミナー 開催記録
なお、同セミナーでは、以下の2つの講演も行われました。ご参照ください。
講演記録②:吉條嘉家氏「SDGsの理念と中小企業にできること」
講演記録③:伊藤武志氏「新たな共感経済・共助社会をどうつくるか」
共助社会と共感経済――『いのち会議』の理念と活動
大阪大学総長補佐/社会ソリューションイニシアティブ(SSI)長
堂目 卓生 氏
0:紹介
まず、自己紹介いたします。私は1988年に大学院を修了しました。専門は経済学の歴史、とくに18世紀の産業革命期の経済思想を研究してきました。いくつかの賞もいただき、研究生活は大変な面もありましたが、今から思えば、その世界に没頭できた幸せな時間だったと思っています。
その後、30年を経た2018年に大阪大学で社会ソリューションイニシアティブ(SSI)というセンターを立ち上げ、代表を務めてきました。SSIは、2050年を視野に、「命を大切にし、一人一人が輝く社会」を目指し、「まもる」「はぐくむ」「つなぐ」という視点から社会課題に取り組む、主に人文学・社会科学系の研究者を中心とした組織です。2023年には「いのち会議」を立ち上げました。副委員長を経て、現在は「いのち会議」事業実行委員会の委員長として、今年の万博で「いのち宣言」の発出を準備しています。
日本SDGs協会_ページ_02-1024x768.jpg)
1:近代社会の基本構造
私は、近代、つまりこの200年から300年のあいだに世界で何が起こり、どのような考え方が根付いたのかを研究してきました。近代において私たちが作った社会像を簡単に示すとどうなるか。私たちが「社会」と聞いて何となく思い描く像は、次のようなものだと思います。
社会の真ん中には「有能な人」がいる。ここで言う「有能」とは、財・サービス・知識の生産に貢献できることです。これは当たり前のように思えるかもしれませんが、実は当たり前ではありません。人類史の長い時間のなかで、生産することに価値が置かれるようになったのは、この200年ほどのことだからです。古代ギリシアのアテネでは奴隷制度があり、生産を担うのは奴隷でした。日本でも士農工商の序列があり、生産を担う農工商は社会の下位に置かれています。中世ヨーロッパでも、上位に位置づけられていたのは聖職者です。財・サービス・知識の生産に貢献する人が社会の中心にいるという構造は、近代の特徴なのです。
日本SDGs協会_ページ_03-1024x768.jpg)
では、近代において、生産に貢献できないとされる人々はどう扱われているでしょう。例えば、子ども・高齢者・障がいや難病のある人、言葉が通じない外国からの人、難民キャンプで暮らさざるを得ない人――こうした人々は「弱者」や「社会的弱者」と呼ばれ、しばしば周辺に追いやられてきました。放置されているわけではなくとも、有能な人が生み出す富や知を「分配してもらう」存在として位置づけられてきたのです。
最近は「包摂(インクルージョン)」という言葉がよく使われます。よい言葉ですが、誰が誰に包摂されるのかはしばしば決められてしまっています。すなわち、弱者が有能な人の仲間入りをさせてもらう、という構図です。子どもは生産的な大人になりなさい、高齢者はいつまでも社会に貢献しなさい、障がいや難病のある人も頑張って雇用されなさい、外国から来た人も文化や言語に馴染み、生産に貢献しなさいというように、(図で)黄色く示す周辺に位置する人々(助けを必要とする側)が青(助ける側)に包摂される、という見取り図です。
2:目指すべき「共助社会」とSDGsの意義
私は、新しい未来社会を考えるにあたり、近代において作ってきた考え方を「反転」させて考えるべきではないかと思うようになりました。つまり、「助けを必要とするいのち」を社会の真ん中に置くということです。「弱者」とは呼ばず「助けを必要とする」、それは人だけでなく、人以外の生き物、自然も含めてです。健康、財産、地位、知識など、助ける手段をたまたま持っている人は、中心に陣取るのではなく、むしろ周辺に退き、そこから真ん中にいるいのちに包摂される。青が黄色に包摂される立場に立ち、手を差し伸べるわけです。
そうすると何が起こるか。実は「助ける側が助けられている」という気づきが生まれます。「助けている人と助けられている人とは実は助け合っている」のです。例えば、介護する人が介護される人から助けられている、という話をよく聞きます。SSIの活動で被災地や高齢者施設、難病のある方々の現場に伺うなかで、私自身がこのことを強く感じました。助ける側と助けられる側との間には、「共助」の関係があるのです。
日本SDGs協会_ページ_04-1024x768.jpg)
加えて重要なのは、青から黄色へは簡単に移りうるということです。昨日まで助ける側にいた人が、今日突然、感染症に罹って集中治療を必要とする存在になるかもしれない。これは新型コロナウイルス感染症で世界が同時に経験しました。地震などの災害でも同じです。昨日まで普通の生活をしていた人が、家を失い避難所で暮らさねばならなくなる。
逆もまた然りで、黄色から青へと立場が変わることもあります。たとえば今年は阪神・淡路大震災から30年ですが、その被災者として助けられた側にいた多くの方々が、1995年の経験を通じて、2011年にボランティアとして東北へ向かった物語が数多くあります。被災し、家族や家を失い、それでも生き延びた人が、今度は同じ境遇の人の話を聴く側に回りました。誰よりも分かるわけですね。自分もかつて同じ状況にいた。そして生き延びた、あるいは生き延びてしまった。そういう人が、津波に家族をさらわれ、財産や家を失い、助けようと思ったのに助けられなかった、そういう体験をした人たちのところで話を聞いています。その結果、「あなたのおかげで生きる気力が湧いた」「助けられた、ありがとう」と言われたとき、今度は助けに行った人が助けられるのです。1995年の時は何もできなかったけれども、家族を失ったんだけれども、でも今後は助けることができた。社会課題の現場は、こういう助け合いの話で満ち溢れています。
ですから私は、助け合いの社会は、「ゼロから作る」「ないものを新しく作る」のではないと考えています。すでにある実践にもっと気がつき、希望を見出し、そこから社会を作り直していきましょうと申し上げているわけです。
これは理想論ではありません。世界もその方向に舵を切っています。それが、まさしく今日のテーマであり、「誰一人取り残さない」を掲げるSDGsです。取り残されている人、取り残されているいのち、取り残されている自然、取り残されている地球のことをまず考える。「助けることができる人」は、「助けを必要とするいのち」を助け、包摂され、結果的に自分も助けられる。そんな風になっていきましょうという考え方が、私たちの捉えるSDGsの意義です。
大阪・関西万博が謳う「いのち輝く未来社会のデザイン」も同様です。まず輝いていないいのちがどこにあるのかを考えるという姿勢ですね。世界が逆風の局面にあるからこそ、共助社会をグローバルに広げる意義、すなわちSDGsの意義は高まっています。
3:「共助社会」を支える「共感経済」
経済の話に移りましょう。
これまでお話した共助社会のお話をすると、「民間企業が本当に支えられるのか?民間企業は収益を上げなきゃいけないし、競争しなきゃいけない。そんな生易しいものではない」とよく言われます。しかし、もし共感をベースにした経済システムを皆で作ることができれば、共助社会を支えられると、私は思います。
「いのち(=助けを必要とする存在)」を支える器には、①民間企業、②中央・地方政府(パブリック・セクター)、③NPO・NGOなどの中間組織(大学を含む)の三つがあります。この3つの経済のそれぞれに、目指すべき「共感経済」を考えることができます。図を示しながら、一つずつ確認してみましょう。
3.1:共感をベースとした「民間経済」
民間経済の主役は、民間企業です。そして、それを支えるのは投資家・労働者・消費者の三者です。
まず、投資家について考えましょう。投資家は、何を基準に資金を投じるのでしょうか。従来は収益率(ROE)でした。しかし、共感経済の観点では、その企業がどれだけ「いのち」を支えているかが基準になります。この「いのち」には、社員、顧客や顧客はもちろん、近隣住民や自然などさまざまなアクターが含まれますね。これらのためにどれだけ配慮し、コストを支払っているかが可視化できれば、そうした企業に優先的に投資する発想が生まれます。これはESG(環境・社会・ガバナンス)投資の流れにも通じます。ただの理想ではなく、すでに実施されているわけです。
では、労働者はどうか。就職先を選ぶ学生を考えればわかりやすいでしょう。初任給や職場の雰囲気ももちろん大切ですが、それだけでよいのか。その企業がいかに「いのち」を支えているかを学び、理解する学生が増えれば、「いのち」を支える企業を選ばれるようになります。そうなれば、企業は良い人を得るためにその点を一層重視するようになります。
最後に、消費者です。消費者は何を基準にものを買うのでしょうか。従来の経済学では「安くて質が良いもの」を前提にしてきました。しかし、別の基準も考えられます。例えば、フェアトレードです。児童労働がないか、プラスチック処理が適正かといったサプライチェーン上の物語が見えるなら、「いのちを支えてきた」ものを口にし、身につけたいという消費者の選択が広がります。そうなれば、そうした努力を重ねる企業が生き残る確率は高まります。
このように、「共感」をベースとした経済を作ることで、民間経済は大きく変わることができます。大阪大学全体、そしてSSIとしても、こうした「見える化」を進め、投資・就労・消費の流れを作っていこうとしています。
日本SDGs協会_ページ_05-1024x768.jpg)
3.2:共感をベースとした「公経済」
経済にはもう一つ、公経済(パブリック・エコノミー)があります。主役は、中央・地方政府です。現在は、日本の国民総支出の約3割がパブリック・サービスに充てられています。
これを支えるのは納税者です。納税は選択の余地がないのですが、納税して終わりではありません。納税者には、税金が適切に使われているかを見届ける責任があります。さらに、「いのち」を支えるためのお金は足りているのか、あるいはお金以外のかたちで何かサポートが必要ではないかと納税者が考えることができる。これがなければ、公経済は成立しません。これは、デモクラシーの課題です。
日本SDGs協会_ページ_06-1024x768.jpg)
3.3:共感をベースとした「連帯経済」
さらに、連帯経済があります。NPO・NGOなどによる財・サービスの提供ですね。これを支えるのが、私たち一人ひとりの市民です。
イタリアやフランスでは国内総生産(GDP)の約一割を占めると言われます。しかし、試算によって異なるものの、日本は1%に満たないとされます。日本のNPO・NGOには、さらなる連帯や自立を通じて価値提供を拡げることができる、大きな伸び代があると考えられるわけです。
日本SDGs協会_ページ_07-1024x768.jpg)
3.4:「いのち」を中心とした共助社会と共感経済
ここまで、共助社会を支える3つの共感経済領域(民間/公/連帯)を概観してきました。それを支えているのは、それぞれ、投資家・労働者・消費者/納税者/市民です。重要なことは、これらの出自がすべて「いのち」であることです。これまでの3つの図で、同じく黄色く色付けしているように、「投資家・労働者・消費者」は「いのち」からの存在です。「納税者」も「市民」も、同じように「いのち」ですね。つまり、共助社会と共感経済を組み合わせたシステムとは、「いのち」が企業・政府・中間組織を用いて「いのち」を支えるシステムだと言えます。これまでの3つの図の上辺と下辺をつなぎ合わせ、ひとつの筒を作ればイメージで切ると思います。
ですから、私たちに必要なのは、「私たちのいのちは私たちで支える」という意識を広げることです。
4:「いのちの声」を聴く――「いのち会議」の取り組み
こうした社会や経済を念頭に、2年前に大阪大学は関西経済連合会・関西経済同友会・大阪商工会議所と共に「いのち会議」を立ち上げました。まず「いのちの声」を聴く。声なき声に耳を傾ける。この態度が極めて大事ですが、簡単ではありません。障がいのある人は、病気のある人は、高齢者を抱えている人は、あるいは虐待された子どもは、そういう声を上げられないでいる人たちは、何を必要としているのかを聞かなければなりません。例えば、その都度アンケートは実施していますが、そこに本音が書かれるとは限りません。誰一人取り残さないと言うなら、ここを外してはいけません。
そのうえで、青の立場(手段を持つ側)が集い、何をしていくかを率直に話し、計画し、実行していく。これらの記録を取り、言語化して残す。それが「いのち宣言」です。一度きりで終えるのではなく、何度も繰り返し、その過程でSDGsの達成を進め、さらに次のゴールを皆で考えていきます。
日本SDGs協会_ページ_04-1-1024x768.jpg)
5:「いのち会議」と「いのち宣言」
これまで50回以上、12のテーマでアクションパネルやワークショップを開催してきました。そして、参加してくださった方々を中心にアクションプランの素案をいただき、それらを「いのち」を「かんじる」「まもる」「はぐくむ」「つなぐ」「しる」という5つのグループに分け、「いのち宣言」を編集しています。
日本SDGs協会_ページ_09-1024x768.jpg)
日本SDGs協会_ページ_10-1024x768.jpg)
「いのち宣言」の前文は次のとおりです。「いのち会議」の思いがすべて込められている言葉です。
私たちに与えられた かけがえのない このいのち
はかなくて 傷つきやすく 時のなかで 変わっていく
どんないのちも 輝きを秘め
すべてのいのちは つながっている
ひとつ ひとつの いのちを
まもり はぐくみ つないでいこう
秘めた輝きを ときはなとう
生きている 意味をしろう
いのちのみなもとに かえろう
いのち会議テーマソング「いのち/INOCHI」について
https://inochi-forum.org/action-report/general-event/theme-song/
この言葉に曲をつけてくださった方がいて、テーマソングとなり、子ども合唱団が歌い始めています。
10月11日には、万博会場のフェスティバル・ステーションで「いのち宣言フェスティバル」というイベントを行います。12時から19時20分までのプログラムのなかで、「いのち宣言」の完成版を披露する予定です。
日本SDGs協会_ページ_12-1024x768.jpg)
現在、100名以上の方から1,500字のアクションプランの素案をお寄せいただいています。これまで何をしてきて、これから何をしていくのか、100の提案をもとに、実行の担い手が誰で、どう進めるかまでを答えられるように整理しています。完成版は120ページほどの冊子になる見込みで、10月に発表します。
しかし、10月で終わりではありません。ここがスタートであり、万博が終わってからが本番です。まずは2030年までにSDGsの達成度を少しでも引き上げる。その先、国連で次のゴール(ポストSDGs)についての議論が始まります。私たちは、万博のレガシーとして、各方面と連携し、JICAなどともつながりながら、「いのち宣言」や「いのちの声」を国連に届け、関西発・日本発で次のゴールづくりに影響を与えていくことを目標としています。そして、2045年までのあいだに、「いのち宣言」で約束したことをどう実現していくかを、ネットワークをさらに拡げながら進めていきたい。壮大な構想ですが、実際に動かなければ世界は本当に危機的な状況になるでしょう。 ぜひ日本SDGs協会のみなさんにもこのネットワークに加わっていただき、共に世界を変え、一緒に構想を現実にしていければと思います。本日は、そうしたお話をざっくばらんにしたいと思います。少し長くなりましたが、以上です。ありがとうございます。
日本SDGs協会_ページ_13-1024x768.jpg)